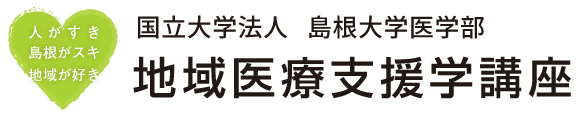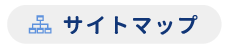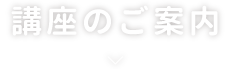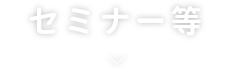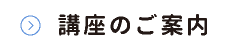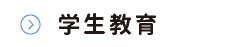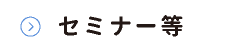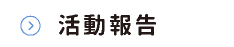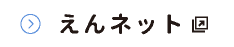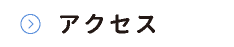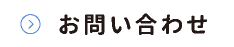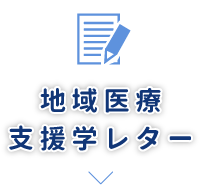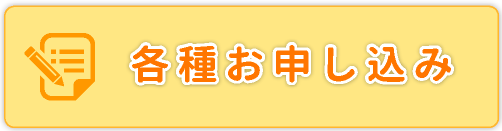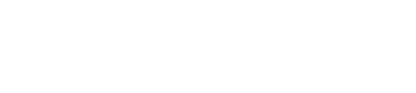気仙沼市立本吉病院 病院長 齊藤 稔哲 先生
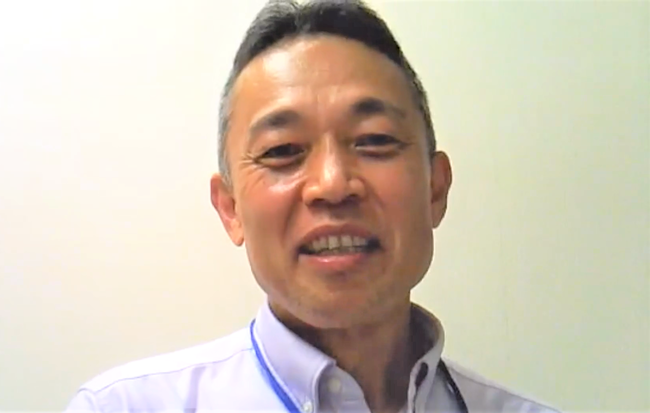
【実施日】令和3年9月3日(金)18:00~19:00
【テーマ】2021年度版 地域の小規模多機能病院について
【講 師】気仙沼市立本吉病院 病院長 齊藤 稔哲 先生
【参加者】21名
【概 要】
今年も齊藤先生に気仙沼市立本吉病院からオンラインでお話し頂いた。
先生は最初に各発達段階における健康度を表した図を示され、各期における大規模病院と小規模医療機関の役割の違いを説明頂いた。病院相互の協力により地域住民には充実した医療が提供され、医療そのものの質も向上するそうである。また受療行動の図を示し「地域医療とは、1000人の住民全てを対象に、200人の外来診療をしながら10人の重篤な病気の発生を予防する活動」と話された。
小規模医療機関は対象の今の健康度だけではなく、生活状況や家族・社会背景を加味し診ていくことを重要視されている。重篤な病気の発生を予防するという視点から、「今困ってないこと」が重要ではなく、将来困ることが起きるような「種」がないか探す必要があると説明頂いた。
続いて、小規模多機能病院である本吉病院のある日の外来をご紹介頂き、対象を限定しない「インフラとしての医療の実践」が印象に残った。生活の中に水道がなければ困る。それと同じように必要な医療を提供し、地域住民の要望に応えておられる。また、健康は生物学的・精神的・社会的な要因からなるという『Bio-Psycho-Social model』について症例を用いて説明頂き、患者さん一人ひとりの背景にあった医療の提供があることを学んだ。
気仙沼市の新型コロナウイルス感染症の対応について、入院患者を受け入れることができない本吉病院ではBPS modelの社会的側面から、入院治療を行う中核病院の負担を減らす為『1.発熱患者の外来診療 2.濃厚接触者の検査を受け入れ 3.コロナワクチンの接種の積極的な実施』の3点を担われている。地域医療とは、欠けているピースを探して、そこを埋めていく作業であり、弱い部分を補強して地域全体のバランスがとれた医療の提供が出来るよう調整していくことが地域医療の在り様であると説明頂いた。そして、今後複合的疾患が増えてくる中で、総合診療医は生物学・精神的側面から抑えることは勿論であるが、社会から人を見ることが重要になってくると述べられた。
最後に地域の総合診療医の役割について、「地域住民の幸せが最大になるように、人を細分化せず一人の人として診察する(中略)幸せの基盤となる生活を住民と一緒に作っていくこと」と説明され、すべてのお話しがここに集約されていることに感動を覚えた。